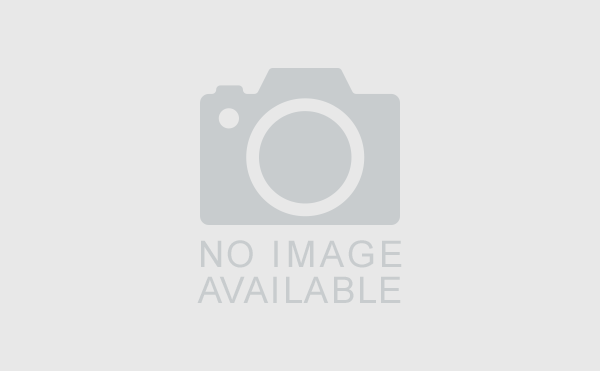演題2.骨髄腫腎の組織型判断に苦慮した一例
演者:恒吉章治,植木研次,松隈祐太,中川兼康,土本晃裕,中野敏昭
九州大学病院腎・高血圧・脳血管内科
本文:症例は65歳女性。脂質異常症に対し,ピタバスタチンを服用していた。2016年12月の健診ではUP(±),UOB (±),Cr 0.83 mg/dLであった。2017年12月の健診でCr 1.00 mg/dL,2018年8月Cr 1.44 mg/dLと腎機能障害が進行した。9月3日前医を受診し,UP(±),UOB(-),血清Cr 1.42 mg/dLであったが,経過観察を指示された。その後腎不全が進行し,10月26日当院腎臓内科に紹介入院した。UP(±),UOB(-),U-Glu (-),UP/UCr 1.3 g/g・Crと尿蛋白定性と定量の乖離を認めた。Hb 7.8 g/dLと正球性正色素性貧血を認め,血清Cr 1.69 mg/dL,UA 3.4㎎/dL,K 3.1 mEq/L,IgG 2640㎎/dL,IgA 38㎎/dL,IgM 36mg/dL,血清および尿蛋白電気泳動でIgGκ鎖が検出され,κ/λ鎖比は96.46であった。頭蓋骨X線写真で,骨打ち抜き像を認めた。骨髄穿刺では,形質細胞の割合は20%で異型を伴っていた。入院第12病日に腎生検を施行した。糸球体に特記すべき異常を認めず,近位尿細管に,HE陽性,PAS陰性の沈着物を認め,上皮細胞の腫大や変性が著明であった。上皮細胞内には結晶成分を認めなかった。Direct fast scarlet (DFS)染色は尿細管上皮細胞に陽性であったが,偏光顕微鏡では陰性であった。免疫染色でも軽鎖やアミロイド蛋白染色は陰性で,電子顕微鏡検査でも細線維構造物を確認できなかった。以上より,アミロイドーシスよりもLight chain proximal tubulopathyの方が可能性が高いと判断した。Bortezomib,Dexamethasone,Cyclophosphamideによる化学療法を開始し,3か月後Cr 0.94㎎/dLまで改善した。
臨床側からの疑問点:
①Light chain proximal tubulopathyの病変として既報で指摘されているような,尿細管上皮細胞内の結晶を本症例では確認できませんでした。本症例をLight chain proximal tubulopathyと分類したことは妥当だったでしょうか。アミロイドーシスや円柱腎症に分類するべきだったでしょうか。
②本症例は、尿細管上皮細胞にDFS陽性の沈着物を認めました。その解釈、あるいはDFS染色の判定方法について御教示いただけませんでしょうか。