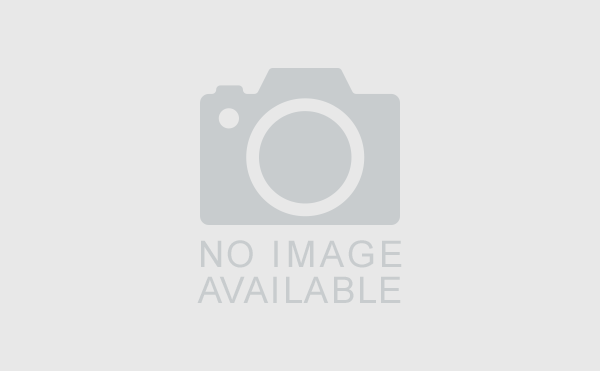演題2 : 尿細管間質障害の病態の解釈に苦慮している多発性骨髄腫の一例
井上 大1)、太田祐樹1) 、牟田久美子1) 、北村峰昭1) 、森 篤史2) 、山下 裕1) 、小畑陽子1) 、西野友哉1)
1) 長崎大学病院 腎臓内科
2) 済生会長崎病院 腎臓内科
コメンテーター 福岡大学腎臓・膠原病内科 升谷 耕介 先生
症例は75歳男性。高血圧症のため近医通院中で、X-2年7月~X-1年5月は、Cr 0.9 mg/dL前後であった。ところが、X-1年9月にはCr 1.1 mg/dL、X年8月にはCr 3.1 mg/dLと腎機能の急速な低下があり、前医へ紹介された。尿蛋白 (1+)、尿蛋白/Cr比 6 g/gCrと尿蛋白定性・定量結果に乖離があり、血中・尿中蛋白免疫電気泳動でλ型Bence Jones蛋白を認め、多発性骨髄腫が疑われたため、9月6日に当院血液内科・当科へ紹介された。骨髄生検では形質細胞率35%であり、BJP-λ型多発性骨髄腫と診断された。
腎生検を施行し、光顕では、糸球体病変は乏しかったが、間質には広範囲にリンパ球主体の炎症細胞浸潤が観察され、局所性に尿細管腔内には無構造なcastを認めた。また、ごく局所性に間質尿細管ではDFS染色陽性の部位があり、過マンガン酸処理で染色性が消失しなかったためALアミロイド蛋白の沈着と考えられた。蛍光抗体法ではλ鎖が尿細管基底膜に線状に染色された。電子顕微鏡所見では、尿細管上皮にアミロイド線維よりもややサイズの小さい線維の沈着を認めたが、軽鎖沈着症の所見は明らかではなかった。
10月下旬より血液内科でBd療法 (ボルテゾミブ・デキサメタゾン) が開始され、尿蛋白/Cr比は9 g/gCr前後から徐々に減少し陰性化し、Crは2.4 mg/dL程度まで改善した。尿中NAGも16.0 U/Lから正常範囲まで低下した。
多発性骨髄腫によるCast nephropathyとアミロイドーシスの合併による腎機能障害と考えられましたが、間質の障害が広範囲にわたっているにもかかわらず、DFS染色陽性の部位やcastの出現がごく局所性であることと、蛍光抗体法で尿細管基底膜にλ鎖が線状に染色されていることから軽鎖沈着症の合併があるのではないかと考えています。
本症例の間質尿細管障害の機序についてご教示をいただければ幸いです。