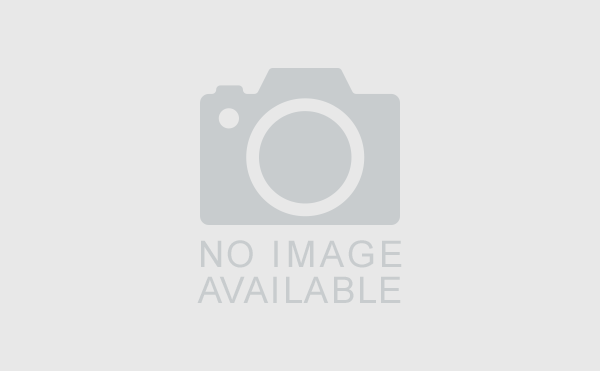演題1:『急速進行性糸球体腎炎の臨床経過を辿った原発性膜性増殖性糸球体腎炎の1例』
1)佐賀大学医学部 腎臓内科、2)同 臨床病態病理学分野
末永敦彦1、水田将人1、山﨑政虎1、福田誠1、力武修一1、宮園素明1、青木茂久2、池田裕次1
コメンテーター 九州大学病院腎疾患治療部 松隈 祐太 先生
【症例】67歳 男性
【既往歴】47歳2型糖尿病、52歳糖尿病性網膜症に対して網膜光凝固、65歳腰椎ヘルニア
【現病歴】検診等で検尿異常を指摘されたことはない。47歳より20年間2型糖尿病で前医かかりつけ。最近のHbA1cは6.0%前後と血糖コントロールは良好であった。2018年2月より浮腫が出現し、徐々に増悪した。3月19日、全身浮腫と体重増加(+6kg)を指摘され前医入院。利尿剤を開始されたが浮腫の改善は乏しかった。前医入院時のCr 0.9mg/dLであったが4月4日にCr 2.2mg/dLまで上昇したため、急性腎不全の精査加療目的に4月5日に当院転院となった。
【入院時血液検査】WBC 14,000/μL(Neu 60.7%、Lympho 9.8%、Eo 23.9%)、TP 5.7g/dL、Alb 2.7g/dL、UN 25.8mg/dL、Cr 2.26mg/dL、CRP 0.73mg/dL、C3 103mg/dL、C4 27mg/dL、CH50 45 /mL、PR3-ANCA 陰性、MPO-ANCA 陰性、抗GBM抗体陰性、HCV抗体陰性、抗核抗体陰性、クリオグロブリン陰性
【入院時尿所見】潜血3+、蛋白3+、UP/UCr 9.96g/gCr
【入院後経過】病歴からは糖尿病性腎症によるネフローゼ症候群も考えられたが、急速進行性糸球体腎炎の臨床像を呈しており、糖尿病性腎症の経過としては非典型的であった。確定診断のために4月10日に腎生検を施行。経過中にCr 4.78mg/dLまで腎不全が進行、乏尿が持続し、肺水腫と胸水による呼吸不全を認めるようになったため4月16日に血液透析を開始した。腎生検標本において、光学顕微鏡では半月体形成はみられず、いずれの糸球体にも分葉化がみられ、メサンギウム細胞の増殖がみられた。メサンギウム基質の増加は目立たず、少数の係蹄内で管内細胞増多がみられた。糸球体基底膜の肥厚はみられず、PAM染色にてspike、bubblingの所見はみられなかった。びまん性に基底膜の二重化を伴うメサンギウム間入がみられた。尿細管間質の線維化は10%程度であった。間質内の小型動脈に血管炎の所見はみられなかった。蛍光抗体法ではIgG、IgM、C3c、C4、C1q、κ、λにおいて糸球体の毛細血管基底膜及びメサンギウム領域の一部に線状あるいは細顆粒状の蛍光像がみられた。電子顕微鏡では上皮下と内皮下に高電子密度沈着物を認めた。以上より病理組織診断はMPGN type3とした。続発性MPGNを想定し全身検索を行ったが明らかな原因を特定できなかった。今回の病歴以前より好酸球増多あり、今回の経過中にも好酸球が経時的に増加しており原因検索を行った。骨髄穿刺で腫瘍性の所見認めず、寄生虫のスクリーニング検査を行うも陰性であった。特発性好酸球増多症の診断となり、腎障害への関与は明らかでなかった。MPGNに対してステロイド治療も検討されたが、糖尿病があることや既に血液透析を要する状態まで腎不全が進行していたこともあり、ステロイド治療は行わなかった。その後も腎機能の改善に乏しく、内シャント造設を施行し維持透析継続の方針とした。
【臨床病理学的疑問点】
原発性MPGNの診断としたが、好酸球との関連など含め、他に鑑別するべき疾患や病態があったか。
MPGNとしては補体低下が無い点が非典型的であるが、どのように解釈するべきか。
本症例に対して何らかの治療介入を行うことはできたか。