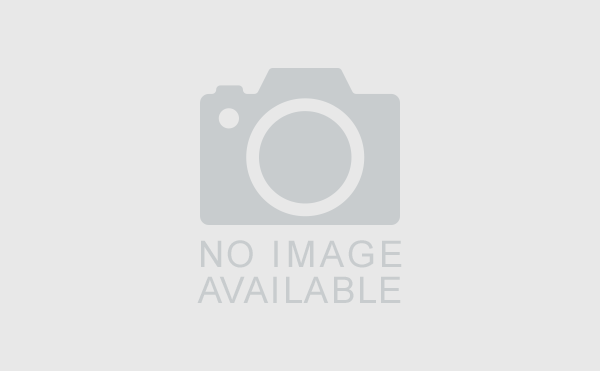演題1:イマチニブによる腎障害が疑われた一例
盛田なつみ1)、横田総一郎1))、渡邊真穂1)、高橋宏治1)、伊藤建二1)、安野哲彦1)、三宅勝久1)、升谷耕介1)、上杉憲子2)、中島衡1)
1) 福岡大学医学部腎臓膠原病内科学 2) 同 病理学
【背景】症例は80歳代男性。X-14年に慢性骨髄性白血病と診断され、当院血液内科でイマチニブによる治療を開始した。治療開始早期より尿蛋白1+が持続し、下腿浮腫が時折出現していた。X-7年より尿蛋白が2+となり、血清Crは1.2mg/dLと軽度上昇した。X-2年に尿蛋白が3+となり、下腿浮腫も増悪したため、血液学的寛解を確認の上、イマチニブを中止した。X-1年2月に血清Crが1.5mg/dLとなったため、当科を紹介受診。紹介時の尿蛋白は4.5g/gCrであり、腎臓病診断確定のため腎生検を施行した。糸球体は14個中4個が全硬化を呈し、メサンギウム細胞増殖は明らかではなかったが、基質の増加を軽度認めた。蛍光抗体法でメサンギウム領域にIgAが陽性と報告されたが、電子顕微鏡では高電子密度沈着物を認めず、広範な内皮障害の所見を認めた。IgA腎症としては非典型的であったが、イマチニブに関連した内皮障害を伴う二次性IgA腎症と診断した。半月体形成など活動性病変を認めなかったため、RA系抑制薬による高血圧治療と食塩摂取制限による保存的治療を行った。その後、尿蛋白1-2g/gCr、Cr 1.3-1.7mg/dLで推移したが、X年10月より尿蛋白が5.5g/gCrに増加し、血清Cr2.3mg/dLと腎機能障害が進行したため、再生検を行った。糸球体27個中17個が全硬化に陥っており、非硬化糸球体の多くに分節性硬化を認めた。蛍光抗体法ではIgAの沈着を認めなかった。二次性巣状糸球体硬化症の診断で保存的加療を継続しているが、腎不全は緩徐に進行している。本症例に関して以下の点につきご討論頂きたく提示する。
【疑問点】
1.2回行った腎生検所見の変化はイマチニブによる腎障害の一連のものと考えて良いか
2.イマチニブを中止して2年以上経過しているのに尿蛋白が再び増加し、病変が進行したのは何故か