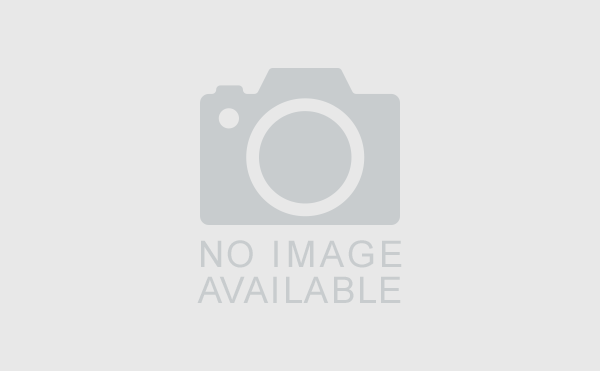第17回 演題2:造血幹細胞移植後にネフローゼ症候群を呈し、多彩な腎病理所見を認めた一例
黒部由佳、阿部伸一、太田祐樹、北村峰昭、浦松正、廣瀬弥幸、小畑陽子、澤山靖、福岡順也、宮崎泰司、西野友哉
長崎大学医学部 腎臓内科、同血液内科、同病理診断科
コメンテーター 福岡大学医学部 病理部 准教授 久野 敏 先生
【症例】45歳 男性
【既往歴】脂肪肝、甲状腺機能低下症
【病歴】X-2年7月に急性骨髄性白血病と診断され、当院血液内科で寛解導入療法(イダルビシン+シタラビン)および地固め療法(1コース目:ミトキサントロン+シタラビン、2コース目:ダウノルビシン+シタラビン)を施行された。末梢血幹細胞移植目的で同年12月に骨髄バンクを介した非血縁者間末梢血幹細胞移植を行い、その後は移植片対宿主病(GVHD)予防としてメソトレキサートを投与された。X-1年1月よりタクロリムス内服へ変更され、タクロリムス漸減してもGVHDの出現がないことを確認し、3月に退院した。その後タクロリムスはX年7月までで0.4 mg/dayに漸減された。
X年5月の検尿では異常がなく、8月の血液検査ではCr:0.78 mg/dl、Alb:4.0 g/dlであった。X年11月上旬より下腿浮腫を自覚し、前医受診したところ、概算尿蛋白:23.02 g/gCr、尿中赤血球:31-50 /HPF、Cr:0.96 mg/dl、TP:5.2 g/dl、Alb:2.0 g/dlとネフローゼ症候群を呈していたため、当科紹介となり腎生検を施行した。光顕所見ではボウマン嚢との癒着を伴う管外性病変を認めた。また、糸球体係蹄内には泡沫状細胞と尿細管極に糸球体係蹄の落ち込みの所見を認めtip lesionと考えられた。PAM染色では基底膜に空胞状変性像やスパイクなどの所見を認めなかったが、蛍光抗体法では、IgGをはじめとして各種グロブリンの係蹄壁への顆粒状沈着を認め膜性腎症の所見であった。さらに、傍尿細管毛細血管にC4dが強陽性で沈着していた。 電子顕微鏡では、上皮下に高密度電子物質を認め膜性腎症Stage Iの所見であり、足突起陥入を認めた。
ネフローゼ症候群の治療としてステロイドパルス療法(メチルプレドニゾロン1 g)に引き続いてPSL60 mg/dayの内服を開始し、タクロリムスは0.4 mg/dayのままで継続した。X+1年1月の時点でPSL50 mg/dayに減量し、概算尿蛋白0.1 g/gCrまで低下しネフローゼ症候群は完全寛解となっている。また、血尿も陰性化している。
【腎生検所見の疑問点】
- 多彩な腎病理所見を認めているが、GVHDに伴うものとして一元的に説明ができるのか。
- 傍尿細管毛細血管にC4dが強陽性となっているが、これはGVHDによるものと解釈してよいのか。
- 今後タクロリムスを増量する必要があると考えているが、カルシニューリン阻害薬の毒性による巣状分節性病変の可能性についてはどうか。
- 管外性の病変は半月体のようにもとらえることができるが、その機序はどのようなものであるのか。
- 足突起陥入を認めているが、本症例での病態との関与や出現機序の解釈はどのように考えればよいのか。