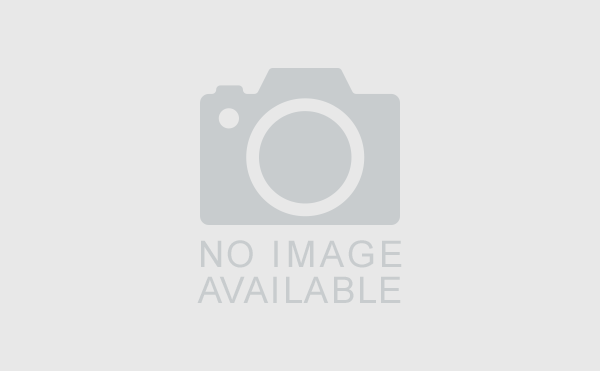第15回 演題1:蛍光抗体法にてIgGの線状沈着を認めた非IgAメサンギウム増殖性腎炎の一症例
中村 奈央、小池 清美、黒川 佑佳、児玉 豪、深水 圭
久留米大学医学部内科学講座 腎臓内科部門
コメンテーター:九州大学大学院医学研究院 臨床教育研修センター助教 土本 晃裕 先生
【症例】59歳 男性
【病歴】2012年7月健診で初めて尿蛋白(+)、尿潜血(-)を指摘され、2013年尿蛋白(2+)、尿潜血(-)、両下腿浮腫出現(体重73kg)、2014年尿蛋白(3+)、尿潜血(2+)と検尿所見は徐々に増悪傾向であったが腎機能は異常なかった。2014年7月健診で初めて血圧:153/94mmHgと高血圧を指摘された。2015年4月(体重:76kg)、手先の痺れを認め近医脳神経外科を受診した際に動脈硬化所見を認め、降圧薬とスタチンを開始された。7月健診で再度尿蛋白(2+)、潜血(2+)を指摘されたため8月に近医循環器内科を受診。随時尿で尿蛋白(2+~3+)、尿潜血(+)、血液検査で低アルブミン血症、IgA上昇を認めたため、慢性糸球体腎炎を疑い当科紹介、ネフローゼ症候群の診断で9月10日に腎生検を行った。
{入院時検査所見:尿蛋白UP/UCr 4.06g/gCr (24時間蓄尿 2.99g/day), T.P 5.73g/dl, Alb 2.58g/dl, IgA 417mg/dl, IgM 59mg/dl, IgG 1216mg/dl, 尿中BJ蛋白検出せず。}
糸球体は22個採取されglobal sclerosis 0個、adhesion 2個、crescent 0個。糸球体はメサンギウム細胞の増多と基質の増加を高度に認めた。基底膜には明らかな変化は認めなかった。尿細管萎縮、間質の線維化、細胞浸潤は軽度であった。IFでは、IgG、κ、λが線状に基底膜に沈着していた(IgGサブクラス:IgG1(+)、IgG2(-)、IgG3(-)、IgG4(+))が、糖尿病の既往はなく、抗GBM抗体は陰性であった。メサンギウム細胞と基質の増加が顕著であり、膜性増殖性糸球体腎炎を疑ったが、低補体血症や基底膜へのC3沈着はなく、電子顕微鏡で高電子密度沈着物は認めなかったため、diffuse global mesangial proliferative glomerulonephritis, non IgAと診断した。
【臨床・病理学的疑問点】
- 今回得られた病理所見(diffuse global mesangial proliferative glomerulonephritis, non IgAの病理診断)で、本症例のネフローゼ症候群は説明がつくでしょうか?
- 糖尿病の既往がなく、抗GBM抗体陰性であった本症例における高電子密度沈着物を認めないIgG線状沈着はどのように解釈したらよいでしょうか?
- 外来加療を継続していますが、ネフローゼの状態が持続しており、今後はIgA腎症に準じたステロイドパルス療法を予定しています。diffuse global mesangial proliferative glomerulonephritis, non IgAに対する治療成績の報告例が少なく、治療方針についてもご教授頂ければ幸いです。
CEN Case Rep. 2017 Nov 27. doi: [Epub ahead of print]
AGEs-RAGE overexpression in a patient with smoking-related idiopathic nodular glomerulosclerosis.